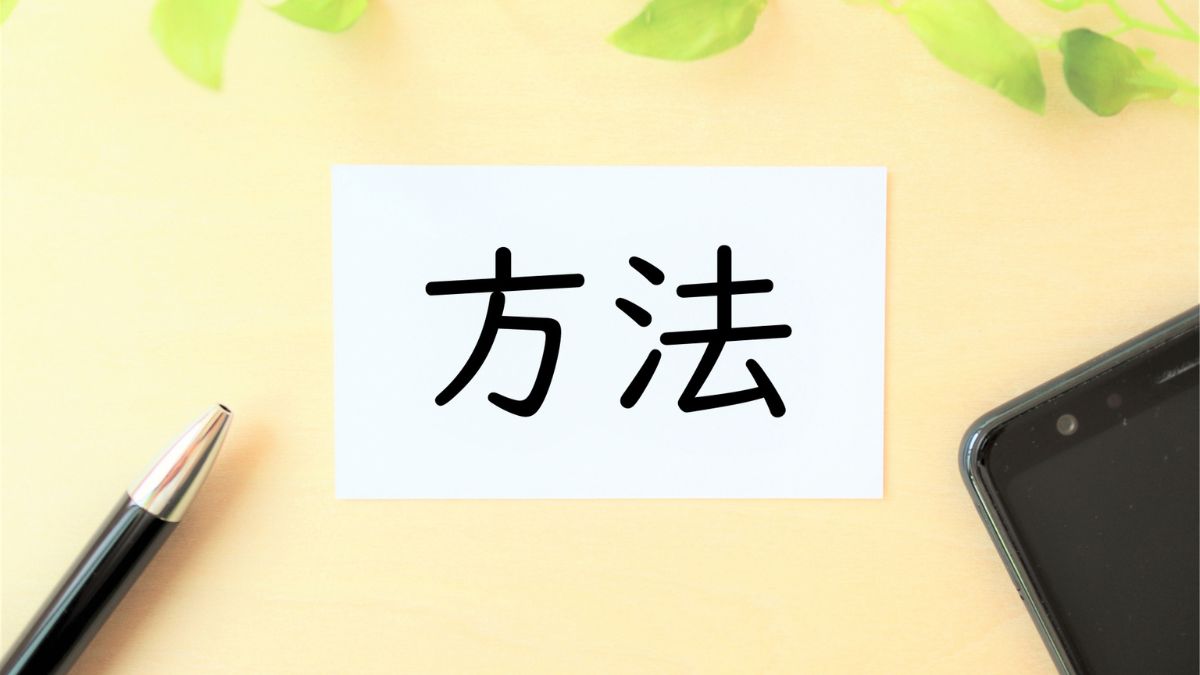BeRealで友達の友達が見れないと悩んでいませんか。
ある日突然「表示されなくなった」「自分だけ見えない」と感じたら、不具合か設定ミスか判断がつかず不安になりますよね。
でも安心してください。
実は、多くのケースではアプリのバグではなく、プライバシー設定や通信環境、アプリのバージョンなどが原因です。
この記事では、BeRealで友達の友達が見れない理由と、その具体的な対処法をわかりやすく解説します。
正しい設定を理解すれば、再び友達の輪を広げるBeReal本来の楽しさを取り戻せます。
ぜひ最後まで読んで、あなたのBeRealを快適に使いこなしてくださいね。
BeRealの友達の友達機能の仕組み

BeRealの友達の友達機能の仕組みを理解することは、見れないときの原因を見極めるためにとても重要です。
それでは詳しく見ていきましょう。
友達の友達機能とは
BeRealの友達の友達機能は、直接つながっていないユーザーの投稿でも、自分の友達を介して閲覧できる仕組みです。
たとえば、自分の友達Aが別の友達Bとつながっている場合、そのBの投稿を「友達の友達」として見ることができるようになります。
これは、完全に公開されている投稿ではなく、限定的な範囲でつながりの輪を広げるような設計になっています。
BeRealは「リアルな人間関係の延長線」を大事にしているため、この機能は単なる閲覧ではなく、信頼関係を前提とした閲覧範囲といえます。
そのため、単に「誰でも見られる」というわけではなく、あくまで友達を通じた限定的な閲覧が可能という仕組みなのです。
表示される条件と制限
友達の友達機能が有効に働くには、いくつかの条件があります。
まず、投稿が「My friends only(友達のみ)」に設定されていないこと。もしこの設定が有効だと、友達の友達には投稿が表示されません。
次に、相手側の「自分の友達リストを他の友達に見せる」設定がオンになっていることが必要です。
これがオフだと、あなたからそのネットワークをたどることができず、結果的に「友達の友達」投稿が見えなくなります。
また、BeRealでは一部の投稿が非公開設定になっている場合もあるため、全ての投稿が必ず表示されるわけではありません。
見える範囲のルール
BeRealでは、友達の友達として見られる投稿にもルールが存在します。
表示される情報は投稿写真やタイムスタンプなどに限られ、コメントやタグ機能は制限されています。
また、投稿主に通知が行くこともほとんどなく、相手は自分の投稿が友達の友達に見られていることを知らない場合が多いです。
つまり、閲覧者側は「軽くつながる感覚」で利用できる一方、投稿者側は「プライバシーを保ったままの限定公開」ができるという構造になっています。
このように、BeRealは信頼をベースにしたコミュニティを意識しており、ユーザー同士が過度に干渉しないデザインがされています。
自分の投稿がどう見られるか
自分の投稿がどの範囲まで見られるかを知ることも大切です。
自分の投稿を「友達のみ」に設定していれば、友達の友達には表示されません。
逆に「友達の友達」に設定しておくと、自分の投稿は自分の友達と、その友達のつながりまで閲覧される可能性があります。
ただし、この範囲はユーザーが自由に設定できるため、常に確認しておくことが大切です。
BeRealは「現実に近いSNS体験」を目指しているため、他のSNSよりも公開範囲が繊細に設計されています。
BeRealで友達の友達が見れない原因

BeRealで友達の友達が見れない原因を徹底的に解説します。
BeRealの「友達の友達」機能が突然見れなくなったときは、焦らず原因をひとつずつ確認していきましょう。
プライバシー設定の変更
BeRealで「友達の友達」が見れない最大の原因は、プライバシー設定が変更されたことです。
特に、自分または友達が投稿を「My friends only(友達のみ)」に設定している場合、その投稿は「友達の友達」に表示されません。
さらに、BeRealには「自分の友達リストを他の友達に見せる」という項目があり、これをオフにしているとネットワークが分断されます。
たとえば、自分がAさん、AさんがBさんとつながっている場合でも、Aさんが「友達リストを非公開」に設定していると、Bさんの投稿はあなたに見えなくなります。
つまり、BeRealの仕組み上、設定ひとつでつながりが途絶えてしまうことがあるのです。
これに気づかず、「バグかも?」と思ってしまう人が多いですが、実は単純な設定変更による影響というケースも多いのです。
通信環境の不安定さ
意外と見落としがちなのが、通信環境の問題です。
BeRealはリアルタイム投稿が特徴のSNSなので、通信が不安定だと投稿データが正しく読み込まれないことがあります。
特にWi-Fiが不安定な環境や、電波の弱い場所では、友達の友達の投稿が途中で読み込み失敗して非表示になることも。
また、画像や動画が多い投稿では読み込みに時間がかかるため、「表示されない」と感じるケースもあります。
この場合は、Wi-Fiとモバイル通信を切り替える、または機内モードをオンオフして再接続することで改善することがあります。
もし他のアプリでも読み込みが遅いと感じたら、通信環境の見直しを優先するとよいでしょう。
アプリのバージョンが古い
BeRealは頻繁にアップデートが行われており、特に「表示系バグ」や「一時的な非表示」などの修正が多く含まれています。
アプリを長期間更新していないと、最新の表示ロジックと異なる処理をしてしまい、友達の友達機能がうまく動かないことがあります。
また、AndroidやiOSのバージョンが古い場合も、互換性の問題が発生してエラーにつながることがあります。
特にAndroid端末では、OSアップデート後にBeReal側がまだ完全対応していない場合、一部ユーザーに限定的なバグが起こることも。
App StoreまたはGoogle Playで最新版に更新し、OS側のバージョンもチェックしておくことがトラブル防止につながります。
サーバーの不具合
BeRealのサーバーが混雑している時間帯や、メンテナンス中の場合にも、「友達の友達」が見られなくなることがあります。
特にアップデート直後や、グローバルユーザーが集中する時間帯(夜など)はアクセスが殺到し、一時的にデータが取得できなくなることも。
このときは、アプリ側の問題であるため、ユーザーができる対処は限られています。
ただ、BeRealの公式X(旧Twitter)やステータスページで障害情報を確認することで、原因を早く知ることができます。
もし周囲のユーザーも同じ現象が起きていれば、サーバー不具合の可能性が高いです。
テスト仕様や一時的な非表示
BeRealはユーザーの一部に限定して新しいUIや機能を試す「A/Bテスト」を頻繁に行っています。
そのため、「他の人には見えているのに自分だけ見えない」という現象が起こることがあります。
一時的に機能が削除されたように見えることもありますが、これはアプリ側の仕様変更を検証しているためです。
この場合は自分では何もできないことが多く、数日後に自然と戻ることもあります。
焦ってアプリを削除するのではなく、しばらく様子を見ることが賢明です。
このように、「BeRealで友達の友達が見れない」ときは、バグよりも設定や仕様によるケースが圧倒的に多いのです。
BeRealの友達の友達が消えたときに確認すべき設定

BeRealの友達の友達が消えたときに確認すべき設定について詳しく解説します。
BeRealの「友達の友達」が見えなくなった場合、バグを疑う前にまず確認したいのがこれらの設定です。
友達リストの公開設定
BeRealの友達の友達機能は、友達リストの公開設定に大きく依存しています。
「自分の友達リストを他の友達に見せる」がオフになっている場合、その人を経由した友達ネットワークが遮断されます。
その結果、あなたから見て「友達の友達」投稿がまったく表示されなくなります。
たとえば、あなたがAさん、AさんがBさんとつながっているとしても、Aさんがリスト非公開にしていれば、あなたはBさんの投稿を見られません。
BeRealはこの仕組みで、意図しないつながりを制限し、プライバシーを守るよう設計されています。
見れない場合は、相手がこの設定を変更していないか確認することが第一歩です。
投稿の公開範囲設定
次に見直すべきは投稿の公開範囲設定です。
BeRealの投稿には「My friends only(友達のみ)」と「Friends of friends(友達の友達)」の2種類があります。
もし投稿が「友達のみ」に設定されていると、当然ながら友達の友達からは見えません。
これは投稿ごとに設定できるため、ある日を境に急に見えなくなった場合は、投稿時の設定変更が原因の可能性があります。
また、相手が一度「友達の友達」で投稿していても、次回以降に「友達のみ」を選んでいれば、非表示になるのは自然な動作です。
確認のためには、自分と相手の投稿公開範囲を一度確認してみましょう。
自分と相手の非公開設定
BeRealの非公開設定は、自分自身や相手の投稿範囲を制限する機能です。
自分の設定が「My friends only」になっていると、あなたの投稿は他人の「友達の友達」リストにも表示されません。
一方で、相手が非公開にしている場合も、あなたはその人を介して他のユーザーの投稿を見られなくなります。
つまり、どちらか一方が非公開設定をしているだけで、「友達の友達」機能の連鎖は途切れてしまうのです。
この設定は意外と見落とされがちですが、機能の根幹に関わる重要な部分です。
アプリのキャッシュと再ログイン
BeRealアプリはキャッシュを使って一時的に投稿データを保存しています。
このキャッシュが壊れたり古くなったりすると、表示される投稿に不具合が出ることがあります。
友達の友達が突然見えなくなった場合、アプリを再起動しても直らないときは、一度ログアウトして再ログインしてみましょう。
それでも改善しない場合は、アプリをアンインストールして再インストールすることでキャッシュがリセットされます。
再ログイン後は設定も確認し直すと安心です。
フレンド削除やブロックの影響
フレンド削除やブロックも、「友達の友達」機能に大きく影響します。
自分または相手が誰かを削除・ブロックすると、そのユーザーを介した投稿は一切表示されません。
つまり、つながりが断たれた時点で、「友達の友達」としての表示も消えるのです。
たとえば、あなたがAさんを削除した場合、Aさんを経由していたBさんの投稿も見えなくなります。
逆にAさんがあなたをブロックしても同じ現象が起こります。
一見関係なさそうに見えても、こうした操作が原因になっているケースも少なくありません。
BeRealで友達の友達が見れないときの対処法

BeRealで友達の友達が見れないときの対処法を5つ紹介します。
BeRealの「友達の友達」が見れないときは、多くの場合ちょっとした設定や環境の問題が原因です。
ここでは、誰でも簡単にできる対処法を順番に紹介します。
プライバシー設定を見直す
まず最初に確認したいのがプライバシー設定です。
BeRealの「友達の友達」機能は、この設定がオフになっていると機能しません。
アプリ右上のプロフィールアイコンをタップして、「設定」→「プライバシー」に進みましょう。
そこにある「友達の友達を表示」「自分の友達を他の友達に表示」という2つの項目をオンにしておくことが大切です。
どちらか一方でもオフになっていると、友達のつながりが遮断されてしまいます。
また、相手側がオフにしている場合も見えなくなるため、確認できる範囲で友達にも協力してもらうと良いです。
設定を変更したらアプリを再起動して反映させてください。
アプリを最新バージョンに更新する
BeRealの不具合の多くは、アップデートで解消されています。
App StoreやGoogle Playを開いて、最新バージョンが公開されていないか確認しましょう。
特に「表示が遅い」「投稿が見えない」といったトラブルは、アプリのロジック修正で改善されることが多いです。
更新後は、一度アプリを完全に閉じて再起動するのがポイントです。
また、スマートフォンのOSが古い場合も、アプリとの互換性で不具合が起こることがあります。
OSの更新も一緒に行うと、BeRealの動作が安定します。
通信環境を整える
BeRealはリアルタイム投稿型のSNSなので、通信環境が安定していないと投稿が読み込まれません。
まずはWi-Fiとモバイルデータを切り替えてみてください。
Wi-Fiが混雑している場合、モバイル通信のほうが安定していることもあります。
逆にモバイル回線が不安定なら、Wi-Fiに接続し直してみるのも効果的です。
それでも改善しない場合は、ルーターの再起動や機内モードのオンオフを試してみましょう。
通信環境を改善するだけで、「友達の友達」が再び表示されるケースは意外と多いです。
アプリを再インストールする
アプリのキャッシュや一時データが破損していると、BeRealの表示に不具合が起こることがあります。
その場合は、一度アンインストールしてから再インストールするのがおすすめです。
再インストールするとアプリの内部データがリセットされるため、キャッシュの破損が原因だった場合は高確率で直ります。
再インストール後は再ログインが必要になるため、登録しているメールアドレスや認証情報を忘れずに確認しておきましょう。
再インストール後に設定を再確認し、「友達の友達」表示がオンになっているかチェックしてください。
時間を置いて再確認する
最後に、時間を置いてから再度アプリを開いてみるのも効果的です。
BeRealはグローバルで利用されているため、サーバーの混雑や一時的なメンテナンスの影響を受けやすいです。
特にアップデート直後や新機能のテスト中は、一時的に「友達の友達」が見えなくなることがあります。
こうした場合、数時間から1日ほど時間をおくと自然に復旧することが多いです。
焦って設定を変えたりアカウントを削除したりする前に、少し待ってみるのが賢い判断です。
もし公式のSNSで不具合報告が出ていれば、しばらく様子を見るのが一番安全です。
BeRealの友達の友達が見れないときにやってはいけないこと

BeRealの友達の友達が見れないときに、ついやってしまいがちなNG行動を紹介します。
焦って間違った対処をしてしまうと、BeRealのアカウントやデータに影響を与えることもあります。
ここでは、やってはいけない4つの行動を解説します。
アカウントをむやみに削除しない
「友達の友達が見れない」と焦ってアカウントを削除する人がいますが、これは一番避けるべき行動です。
BeRealのアカウントを削除すると、友達リストや過去の投稿データがすべて消えてしまいます。
再登録しても元のつながりは自動で戻りませんし、友達の友達機能が再び使える保証もありません。
実際、多くの場合は設定や一時的な不具合が原因なので、アカウント削除をする必要はないのです。
もしどうしても直らない場合は、アプリ内の「お問い合わせ」からサポートに連絡するのが正しい対応です。
サードパーティアプリを使わない
BeRealのデータを外部アプリで見ようとするのも危険です。
「友達の投稿を見られる」などとうたう非公式アプリやWebサービスは、多くが不正アクセスや情報漏えいのリスクを伴います。
BeRealはプライバシーを非常に重視しているSNSなので、外部連携を許可していません。
そのため、こうしたツールを使うとアカウント停止やデータ流出の危険があります。
安全に使うためにも、公式アプリのみを利用するようにしましょう。
設定を無闇に変えすぎない
見えないからといって、設定を片っ端から変えるのもおすすめできません。
BeRealは設定が相互に関係しており、ひとつ変えると他の項目にも影響が出ることがあります。
特に「友達の友達を表示」や「非公開設定」を何度も切り替えると、サーバーとの同期が遅れて混乱を招くことがあります。
設定を見直す際は、ひとつずつ確認して、変更後にアプリを再起動するのがポイントです。
短時間で何度も変更するのではなく、落ち着いて順番に確認していくようにしましょう。
他人の情報をスクリーンショットで拡散しない
「友達の友達」の投稿を見つけたときに、スクリーンショットを撮ってSNSに載せる行為も避けてください。
BeRealのコンセプトは「リアルで安心できる日常の共有」です。
他人の投稿を無断で拡散すると、プライバシー侵害になるおそれがあります。
特に顔や生活の一部が写っている投稿を第三者に公開するのはマナー違反です。
BeRealは信頼関係を基盤とするSNSなので、他人の投稿は「見て楽しむだけ」に留めるのが正しい使い方です。
まとめ|BeRealの友達の友達が見れないときの原因と対処法
| 確認すべきポイント | ページ内リンク |
|---|---|
| 友達リストの公開設定 | こちら |
| 投稿の公開範囲設定 | こちら |
| 自分と相手の非公開設定 | こちら |
| アプリのキャッシュと再ログイン | こちら |
| フレンド削除やブロックの影響 | こちら |
BeRealで「友達の友達」が見れないときは、多くの場合、アプリのバグではなく設定や通信環境が原因です。
特に「プライバシー設定」や「友達リストの公開設定」は、ちょっとした変更で見え方が大きく変わります。
また、アプリのバージョンが古いままだと機能がうまく動作しないこともあります。
焦ってアカウントを削除する前に、まずは設定の見直しや再インストール、通信環境の確認を試してみてください。
もしそれでも解決しない場合は、BeReal公式のSNSやサポートに問い合わせて状況を確認するのが安心です。
BeRealは「リアルなつながり」を大切にするSNSです。設定を理解して上手に使えば、安心して楽しく交流を広げることができます。
参考リンク: